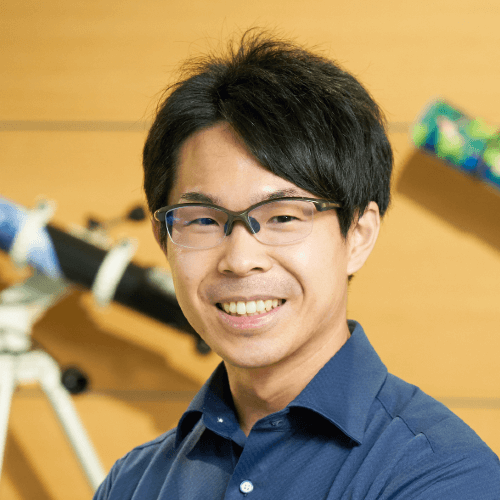大学院時代には、天文学を専攻していた森裕樹さん。高エネルギーニュートリノという珍しい粒子を放出する天体を見つけるべく、共同研究に従事。見事、世界で初めて放射源天体の観測に成功し、その共同研究成果論文はサイエンス誌にも掲載された。卒業後の進路も、宇宙産業にも関われる大手総合ITメーカーを選択。
ここまで見れば、まさに「宇宙」一辺倒のキャリア。しかし、入社後わずか2年も経たずに1社目を飛び出し、一般財団法人リモート・センシング技術センター(以下「RESTEC」と記載)へ転職。職種もインフラエンジニアからデータサイエンスを扱う研究員へと様変わりした。
果たして、その大きな決断の裏にはどのような思いがあったのか。そこまで彼を惹きつけたRESTEC、そしてデータサイエンスの魅力とはなんだったのか。森さんの率直な想いを伺った。
宇宙には関わりたいが、縛られたくはなかった。
新卒で入社した会社を2年も経たずに飛び出し、新天地へと向かった森さん。しかも、インフラエンジニアからデータサイエンスを扱う研究員への異職種の転職。側から見れば、疑問に思う部分もあるだろう。しかし、その端緒は在学時から顔を見せていたという。 「たしかに、ずっと天文学を専攻してきましたし、宇宙は今も大好きです。しかし、とにかく宇宙のことだけ考えていたいというタイプではありませんでした。宇宙には関わりつつも、幅広い仕事を経験したいと考えていました。1社目に総合ITメーカーを選んだのも、宇宙関連の事業がありつつも、他にも様々な事業を展開していたからです。」 多様な事業展開をしており、採用もコース別ではなく総合職。当然、宇宙に関連しない部署への配属可能性も織り込んだ上で、幅広い可能性に惹かれて入社を決めた。しかし、想定していたとはいえ、実際に全く異なる部署へ配属されると徐々に違和感を覚えていったという。 「1社目では、自治体向けのサーバーインフラの整備やリプレースを担当していました。いわゆるインフラエンジニアです。宇宙には全く関係のない部署ですね(笑)。これはこれで貴重な経験ですから、1年ほどしっかり学んで宇宙関連の部署へ異動希望を出そうと思っていたのですが、会社からは『4、5年はそこで学びなさい』と言われました。そんなに頻繁に部署を異動していたら専門性が身に付きませんから、今思うと当然ですよね。」
![[046]Project-Stories-1](https://images.ctfassets.net/7z4do5alg1qg/8jwDHcxbLDIeE8ir80WE3/6352c22215a705ce1c5ee1a8cfbed508/-046-Project-Stories-1.png)
ITならではの先端技術や、それを活かしたアイデアを仕事に反映させたかった。
宇宙に関われずとも、仕事は楽しめるはず。そう考え直して目の前にある業務に向き直った森さんだが、違和感はますます強まっていった。その原因は宇宙に関係なく業務の進め方にあった。 「ITは技術の進歩が目覚ましい。その新しい技術を取り込みながら何ができるかを考えるのも楽しいかもと思ったのです。ところが、クライアントが自治体ということもあり、仕事の進め方やソリューションもある程度決まったものになってしまう。高い信頼性が求められる以上、仕方のないことではあるのですが、もう少し自由度高く、自分のアイデアを織り交ぜながら仕事がしたいという気持ちが大きくなっていきました。」 会社でできないなら、社外で。そう思い、技術やデータを活用したアイデアを競うハッカソンに参加するようになった森さん。そこで、RESTECと出会うこととなる。 「衛星データを活用してソリューション提案するハッカソンにいくつか参加して、その中で何度かRESTECという名前を目にしました。気になって調べたところ、新卒採用の募集がかかっていた。しかも、第二新卒も対象で、自分も条件に合致している。運命のようなものを感じて、すぐに応募しました。」
![[046]Project-Stories-2](https://images.ctfassets.net/7z4do5alg1qg/2ASlPYxXAVx6nvFsYNvKZl/6a68968d0542f289392adea3d893a37e/-046-Project-Stories-2.png)
AIの実務経験はゼロ、相談できる相手もいない中での試行錯誤。
1日のうちに部長面接と役員面接を受け、その帰りの新幹線内で合格通知を受けるという凄まじいスピードで入社が決まった。そんな会社からの期待に応えるように、今はやりがいを感じながらイキイキと働いているという。 「現在メインで担当しているのは、AIと衛星データを組み合わせて、新しい技術を生み出せないかという研究です。具体的には、中央省庁と共同で、農地の形状変化を抽出しています。衛星から撮影した農地の俯瞰画像をAIで処理して、昨年度のデータと比較しながら形状が変化した部分を自動でピックアップする『筆ポリゴン自動変化抽出※』というソリューションを開発しています。」 衛星データという形で宇宙にも関わることができる。筆ポリゴン自動変化抽出の精度を上げるために、自由な発想で試行錯誤をする毎日。まさに森さんがやりたかった仕事そのものだ。しかし、業務が順風満帆に進んでいるかというとそれはまた別の話だ。 「ここまで辿り着くのも一苦労でした。弊社にはAIの専門家がおらず、わからないことを聞ける相手もいない。頼みの綱は、前任者が残したコードだけ。そのコードをひたすら解読し、わからないことは調べながら手探りで進めてきました。少しコードを変えてみては、結果の変化と照らし合わせて地道に改善を続けて、なんとか形にできたというところです。」 ※筆ポリゴン:耕地面積調査等の母集団情報として、全国の土地を隙間なく200メートル四方(北海道は、400メートル四方)の区画に区分し、そのうち耕地が存在する約290万区画について衛星画像等をもとに筆ごとの形状に沿って作成した農地の区画情報。農林水産省と産業技術総合研究所により共同研究で、農林水産省から委託を受けRESTECが代表機関として研究を行っている。
![[046]Project-Stories-3](https://images.ctfassets.net/7z4do5alg1qg/6JsWltMY7mqFWziieBsvuQ/7ea9128e3cc54ce1f73b07e8d649d686/-046-Project-Stories-3.png)
この仕事は、自分にとっての天職だと思う。
AIに関して頼れる先輩もおらず、自身もAIに関する実務経験はゼロ。そんな状況でも、毎日が充実しているという。それは、顧客への提供価値や事業やソリューションの社会的意義といった高尚なものだけではなく、シンプルな業務の面白さゆえだ。 「日を追うごとに精度が上がっていくのが、目に見えてわかります。これがたまらなく楽しい。どうやったら精度が上がるかを自分で考えて、それを試して、成果が数字で表れる。そしてまた、さらに精度を上げる方法を考えて、というこのサイクルを回すのが本当に面白いです。しかも、そこで扱うデータが宇宙関連のものですから、まさに天職だと思っています。」 仮説を立て、実装し、検証する。そのサイクルを楽しむことで、結果的に顧客や社会のためにもなるという、さらに大きなサイクルが回っていく。森さんの知的好奇心を中心に、まるで衛星のように好循環が回っている。これは、理想的な仕事の形の一つと言えるのではないだろうか。それが実現できているのは、きっとAIに縛られすぎずに、自分が大好きな宇宙とAIを掛け合わせて新しい価値を生み出しているから。専門的にAIを学んできた経歴がなくても、自分の好奇心が向かう対象とAIを組み合わせれば活躍できる。森さんは、今日もそれを証明するかのように、目を輝かせながら働いていることだろう。
今後の目標
RESTECではAIを用いた業務を本格化している最中なので、まずは周りに「AIで困ったら森に聞こう」と思われるような存在になりたいですね。そうやって技術と信頼を積み重ねて、マネジメントも任されるようになるのが、今の目標です。マネージャーになっても現場からは離れることなく、エンジニアリングのスキルとマネジメントのスキルを兼ね備えたビジネスパーソンになれれば最高ですね。